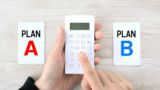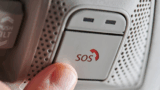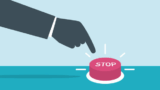「認知症の家族が徘徊してしまい、いつも警察にお世話になっている」「GPS機器を持たせても忘れて出かけてしまう」「靴につけるGPSって本当に効果があるの?」
認知症による徘徊は、ご家族にとって最も心配な症状の一つです。特に、何も持たずに外出してしまう認知症の方にとって、従来のGPS機器では対応が困難な場合が多くあります。
この記事では、認知症の徘徊対策として注目されているGPSを靴につけるタイプの特徴や選び方、効果的な活用法について詳しく解説します。専用GPS靴から後付けタイプまで、あなたの状況に最適な選択肢を見つけるための完全ガイドをお届けします。
【2026年版】高齢者見守りサービスランキング。タイプ別に比較
認知症の徘徊対策でGPSを靴につける理由とメリット
なぜ認知症の徘徊対策において、GPSを靴につけるタイプが注目されているのでしょうか。その理由と具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
靴につけるGPSが選ばれる3つの理由

認知症の方の徘徊対策でGPSを靴につける最大の理由は、装着の自然さにあります。認知症の方は新しいものや馴染みのないものを身につけることを嫌がる傾向がありますが、靴は日常的に履くものなので抵抗感が少ないのです。
2つ目の理由は、紛失リスクの軽減です。腕時計型やペンダント型のGPS機器と違い、靴は外出時に必ず着用するため、置き忘れや外し忘れの心配がありません。実際に、認知症の方の多くは手ぶらで外出することが多く、持ち物タイプのGPS機器では追跡が困難になります。
3つ目は、本人の尊厳を守ることです。GPS機器が靴の内部に隠れているため、外見上は普通の靴と変わらず、本人が「監視されている」という感覚を抱きにくいという利点があります。
バンド型GPSとの比較でわかる靴タイプの優位性

腕時計型やバンド型のGPSと比較すると、靴につけるタイプの優位性がより明確になります。
バンド型GPSの場合、認知症の方が「これは何だろう?」と疑問に思い、外してしまうケースが頻繁に発生します。また、入浴時や就寝時に外す習慣があるため、その際に再装着を忘れてしまうリスクもあります。
一方、靴につけるGPSは外出時に自然に携帯されるため、追跡の確実性が高いのです。ただし、複数の靴を使い分けている場合は、全ての靴にGPS機能を付ける必要があるという課題もあります。
充電や交換の面では、バンド型の方が取り外しやすく便利ですが、靴タイプも最近では充電しやすい構造になっているものが増えています。
比較ポイント:靴 vs バンド型
【装着率】靴◎ バンド△
【自然さ】靴◎ バンド△
【充電】靴△ バンド◎
【価格】靴△ バンド◎
【防水性】靴◎ バンド○
認知症の方に負担をかけない自然な装着方法

認知症の方にGPS機器を自然に装着してもらうには、いつもの生活習慣に組み込むことが重要です。靴であれば、外出時の自然な流れで装着できるため、本人にとってストレスが少ないのです。
特に効果的なのは、本人が普段愛用している靴にGPS機能を後付けする方法です。馴染みのある靴であれば、違和感なく履いてくれる可能性が高くなります。
また、靴を履く際の重量感の変化を最小限に抑えることも大切です。最新のGPS機器は小型軽量化が進んでおり、装着しても歩行感覚にほとんど影響しないレベルまで改良されています。
GPS靴の種類と靴につける方法を詳しく解説
GPS機能を靴につける方法には、いくつかのタイプがあります。それぞれの特徴を理解して、最適な選択をしましょう。
専用GPS靴と後付けタイプの特徴と選び方

専用GPS靴は、製造段階からGPS機能が組み込まれた靴です。最も代表的なのは「iTSUMO」ブランドのトレッキングシューズで、足の甲の内側にGPS端末を挿入する独自設計が特徴です。
専用GPS靴のメリットは、GPS機能の統合性が高く、防水性能や耐久性に優れていることです。また、充電ポートの位置や操作性も最適化されています。
一方、後付けタイプは、既存の靴にGPS端末を後から装着する方法です。靴の改造サービスを利用して、かかと部分や中敷きにGPS機器を埋め込みます。
後付けタイプの最大の利点は、本人の好みの靴を使えることです。認知症の方は特定の靴に愛着を持っている場合が多く、その靴を使い続けられることで装着率が向上します。
中敷きタイプとシールタイプの使い分け

GPSを靴につける具体的な方法として、中敷きタイプとシールタイプがあります。
中敷きタイプは、GPS端末を中敷きに組み込んだもので、靴の中に入れるだけで使用できます。複数の靴で使い回しができるため、経済的なメリットがあります。また、取り外しが簡単なので、充電やメンテナンスも楽に行えます。
シールタイプは、GPS端末をシール状にして靴の内側に貼り付ける方法です。非常に薄型で、履き心地への影響が最小限です。ただし、粘着力の低下により定期的な貼り替えが必要になる場合があります。
どちらを選ぶかは、認知症の方の歩行状態や靴の使用頻度によって決まります。活発に歩き回る方には耐久性の高い中敷きタイプ、足腰が弱い方には薄型のシールタイプが適しています。
既存の靴への加工サービスと持たせ方のコツ

既存の靴にGPS機能を追加する加工サービスは、「魔法の靴」などの専門業者が提供しています。このサービスでは、お気に入りの靴を業者に送り、かかと部分にGPS端末を埋め込んでもらえます。
加工サービスのメリットは、本人が愛用している靴をそのまま使えることです。認知症の方は環境の変化を嫌う傾向があるため、馴染みの靴を使い続けられることで、装着への抵抗が大幅に減ります。
効果的な持たせ方のコツとしては、まず他の靴を一時的に隠すことが重要です。GPS付きの靴しか選択肢がない状況を作ることで、確実に装着してもらえます。
また、GPS機能について本人に詳しく説明する必要はありません。「新しく修理した靴だよ」程度の軽い説明で十分です。過度な説明は本人の不安を煽る可能性があります。
【保存版】高齢者見守りペンダントの選び方は?安全な使い方と注意点
認知症GPS靴を選ぶ際の重要なポイント
GPS靴を選ぶ際は、技術的な仕様だけでなく、実際の使用場面を想定した選択が重要です。以下の観点から詳しく検討しましょう。
位置精度と通信機能で比較する選定基準

GPS靴の最も重要な機能は、正確な位置情報の取得です。現在の高精度GPS機器では、誤差3~5メートル程度で位置を特定できます。
位置情報の更新頻度も重要な要素です。リアルタイム追跡が可能な機器では、1分から5分間隔で位置情報を更新します。徘徊の早期発見には、更新頻度が高い機器が有効です。
通信機能としては、スマートフォンアプリとの連携機能が基本となります。家族が複数人いる場合は、複数のスマートフォンで同時に位置を確認できる機器を選ぶことが重要です。
さらに高機能な機器では、設定したエリアから外れた際の自動通知機能や、移動手段(徒歩・バス・電車)の判別機能も搭載されています。これらの機能により、より詳細な行動パターンを把握できます。
必須機能のチェックポイント
✓ GPS精度:誤差5m以内
✓ 更新頻度:5分間隔以下
✓ 複数端末対応:家族全員で共有
✓ エリア通知:設定範囲外への警告
✓ バッテリー警告:充電タイミングの通知
充電方式と防水性能の確認ポイント

充電方式は、継続使用において非常に重要な要素です。靴に内蔵されたGPS端末は、取り外しが困難な場合があるため、充電の容易さを事前に確認する必要があります。
最近の機器では、USB充電式が主流となっています。充電ポートが靴の外側からアクセスしやすい位置に配置されているかを確認しましょう。また、充電時間とバッテリー持続時間のバランスも重要です。
一般的なGPS靴のバッテリー持続時間は、3日から7日程度です。認知症の方の外出頻度や活動レベルに応じて、適切な持続時間の機器を選択します。
防水性能については、IPX7以上の防水等級を推奨します。これにより、雨天時の外出や靴の洗浄時にも安心して使用できます。特に、認知症の方は天候に関係なく外出することがあるため、防水性能は必須機能と考えるべきです。
【保存版】一人暮らしの老人の緊急ボタンの選び方。安全な活用法は?
費用対効果と継続利用のための考慮事項

GPS靴の導入には、初期費用と継続費用の両方を考慮する必要があります。
初期費用は、専用GPS靴で5万円から10万円程度、後付け加工サービスで3万円から5万円程度が相場です。中敷きタイプやシールタイプの簡易版では、1万円から3万円程度で導入可能です。
継続費用として、月額通信料が発生します。多くのサービスで月額500円から1,500円程度の通信費がかかります。年間で考えると6,000円から18,000円程度の継続費用となります。
費用対効果を考える際は、徘徊による捜索コストと比較することが重要です。警察や消防署による捜索活動や、家族の時間的負担、精神的ストレスを総合的に評価すると、GPS靴の導入メリットは大きいと言えます。
継続利用のためには、靴の耐久性も重要な要素です。認知症の方は歩行量が多い場合があり、靴底の摩耗により買い替えが必要になることがあります。耐久性の高い靴を選ぶことで、長期間の使用が可能になります。

GPS靴は便利ですが、万能ではありません。認知症の進行に伴い、靴を履かずに外出することもあります。他の見守り方法と組み合わせることが大切ですね。
在宅介護で家族の負担を軽減するには?持続可能な介護体制の構築法
認知症GPS靴の効果的な活用法と注意点:まとめ
認知症の徘徊対策として、GPSを靴につけるタイプは非常に効果的な選択肢です。特に、何も持たずに外出してしまう認知症の方にとって、確実に携帯できる見守りツールとして大きな安心感を提供します。
専用GPS靴と後付けタイプ、それぞれに特徴があり、認知症の方の状態や家族の状況に応じて最適な選択が可能です。本人の靴への愛着を考慮した選択が、装着率の向上につながります。
技術的な面では、位置精度、通信機能、充電方式、防水性能を総合的に評価することが重要です。継続使用のためには、費用対効果と耐久性も十分に検討する必要があります。
GPS靴は徘徊対策の強力なツールですが、万能ではありません。認知症の進行に伴い、靴を履かない外出や環境への適応困難が生じる可能性もあります。そのような場合は、専門家への相談や他の支援策の検討が必要になるでしょう。
認知症の徘徊対策は、一つの方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることが大切です。GPS靴をはじめとする見守り技術を活用しながら、家族だけで抱え込まない支援体制を構築していきましょう。専門的なアドバイスが必要な場合は、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談することをお勧めします。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。