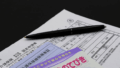「デイサービスとデイケアって何が違うの?」「親にはどちらが合っているのかわからない」「費用や利用条件に違いはあるの?」
在宅介護を始めるとき、通所系サービスの選択は重要な決断です。しかし、デイサービスとデイケアの違いがよくわからず、どちらを選べばよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、デイサービスとデイケアの違いを詳しく比較し、それぞれの特徴、メリット・デメリット、費用、選び方のポイントまで、わかりやすく解説します。あなたの大切な家族に最適なサービスを選択するための判断材料を提供いたします。
デイサービスとデイケアの基本的な違い
デイサービスとデイケアは、どちらも自宅から通って利用する介護保険サービスですが、目的やサービス内容に大きな違いがあります。まずは基本的な特徴を理解しましょう。
デイサービスの基本概要と目的

デイサービス(正式名称:通所介護)は、日常生活上の介護や心身機能の維持、社会交流を目的とした介護保険サービスです。利用者が施設に通い、入浴、食事、排泄介助などの基本的な介護を受けながら、レクリエーション活動や軽い機能訓練を行います。
主なサービス提供者は介護職員で、生活相談員やケアマネジャーが中心となって日常生活の支援を行います。医師や看護師が常駐していない施設も多く、「生活支援」に重点を置いたサービス内容となっています。
デイサービスは、在宅での生活を継続するための支援と、家族の介護負担軽減を重要な目的としています。利用者同士の交流やレクリエーション活動を通じて、社会参加の機会を提供し、生活の質の向上を図ります。
デイケアの基本概要とリハビリの特徴

デイケア(正式名称:通所リハビリテーション)は、医師の指示に基づく専門的なリハビリテーションを通じて、身体機能の維持・回復や自立支援を目的とした介護保険サービスです。
デイケアの大きな特徴は、医師、看護師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの医療・リハビリ専門職が常駐していることです。医学的管理のもとで個別リハビリや集団リハビリが提供され、利用者一人ひとりの状態に応じたプログラムが実施されます。
病院や介護老人保健施設、クリニックなどの医療機関で提供されることが多く、退院後の継続的なリハビリや、病気や怪我による身体機能低下の改善を重視しています。
デイサービスとデイケアの根本的な違い

デイサービスとデイケアの根本的な違いを整理すると、以下の通りです:
デイサービス(通所介護)
– 目的:生活支援・社会交流・家族負担軽減
– 中心スタッフ:介護職員・生活相談員
– 医療体制:医師不在の施設も多い
– 対象:要介護1~5(医師の指示不要)
– 特徴:アットホームな雰囲気、レクリエーション充実
デイケア(通所リハビリテーション)
– 目的:機能訓練・身体機能の維持回復・自立支援
– 中心スタッフ:医師・看護師・リハビリ専門職
– 医療体制:医師常駐または定期診療
– 対象:要支援1・2、要介護1~5(医師の指示必要)
– 特徴:専門的リハビリ、医学的管理
このように、「生活支援中心」のデイサービスと「リハビリ中心」のデイケアという明確な違いがあり、利用者の状態やニーズに応じて選択することが重要です。
デイサービスの詳細―サービス内容・メリット・対象者
デイサービスについて、より詳しく見ていきましょう。利用を検討している方にとって重要な情報をお伝えします。
デイサービスの具体的なサービス内容

デイサービスでは、日常生活に必要な様々なサービスが提供されます。
基本的な介護サービスとして、入浴介助、食事介助、排泄介助、移動・移乗介助などが行われます。特に入浴サービスは、自宅では困難な方にとって非常に重要なサービスです。個別浴槽や機械浴など、利用者の身体状況に応じた入浴方法が選択されます。
レクリエーション活動も充実しており、季節の行事、音楽療法、手工芸、書道、園芸活動など多彩なプログラムが用意されています。これらの活動は認知症予防や社会参加の促進に効果的です。
機能訓練では、理学療法士や柔道整復師等による軽度の運動指導や体操が実施されます。ただし、デイケアのような専門的な個別リハビリテーションとは異なり、集団での軽運動が中心となります。
送迎サービスも重要な要素で、自宅から施設まで専用車両で送迎が行われます。車椅子対応車両や介護職員による乗降介助も提供されます。
デイサービスのメリットと魅力

デイサービスには、利用者と家族にとって多くのメリットがあります。
家族の介護負担軽減が最大のメリットです。日中の数時間、専門スタッフに介護を任せることで、家族は仕事や用事、休息の時間を確保できます。特に入浴介助は家族にとって大きな負担となるため、施設で安全に入浴できることは非常に価値があります。
社会交流と孤立防止も重要な効果です。同世代の利用者との交流やスタッフとのコミュニケーションにより、社会的なつながりを維持できます。これは認知症の進行抑制や精神的な健康維持に大きく寄与します。
生活リズムの維持も期待できます。定期的な外出と活動により、昼夜逆転の予防や規則正しい生活習慣の維持が図られます。
利用開始の手軽さもメリットの一つです。医師の診断書が不要で、ケアマネジャーを通じて比較的スムーズに利用開始できます。急な利用ニーズにも対応しやすい特徴があります。
デイサービスの注意点と制限事項

一方で、デイサービスにはいくつかの制限や注意点もあります。
医療的ケアの制限が最も重要な注意点です。医師が常駐していない施設が多いため、高度な医療的処置や緊急時の医学的対応には限界があります。インスリン注射や経管栄養などの医療行為は、施設によって対応可否が大きく異なります。
個別リハビリの限界もあります。機能訓練は提供されますが、デイケアのような専門的で個別性の高いリハビリテーションは期待できません。身体機能の大幅な改善よりも、現状維持が中心となります。
環境への適応が困難な場合もあります。認知症の方の場合、新しい環境や多くの人がいる場所で混乱や不安を感じることがあります。施設の雰囲気や他の利用者との相性も重要な要素となります。
デイケアの詳細―専門的リハビリ・医療体制・対象者
続いて、デイケアについて詳しく解説します。デイサービスとの違いを明確に理解していただけるよう、具体的な内容をお伝えします。
デイケアで提供される専門的リハビリテーション

デイケアでは、医師の指示のもとで専門的なリハビリテーションが実施されます。
理学療法(PT)では、歩行訓練、筋力強化、関節可動域訓練、バランス訓練などが行われます。脳梗塞後の麻痺改善、骨折後の機能回復、廃用症候群の予防など、個々の身体状況に応じたプログラムが作成されます。
作業療法(OT)では、日常生活動作の練習、手指の巧緻性訓練、認知機能訓練、福祉用具の使用練習などが実施されます。食事、更衣、入浴などの基本的ADLから、調理、掃除などの応用的ADLまで幅広く対応します。
言語聴覚療法(ST)では、失語症や構音障害の改善、嚥下機能訓練などが行われます。脳血管障害による言語障害や、加齢による嚥下機能低下に対応した専門的な訓練が提供されます。
これらのリハビリは個別訓練と集団訓練を組み合わせて実施され、利用者の目標に応じてプログラムが調整されます。
デイケアの医療体制と安全管理

デイケアの大きな特徴は、充実した医療体制にあります。
医師の配置により、利用者の健康状態の継続的な管理が行われます。定期的な診察や血圧・血糖値の測定、薬剤管理などの医学的ケアが提供されます。急な体調変化にも迅速に対応できる体制が整っています。
看護師の常駐により、日常的な健康チェックや医療的処置が可能です。血圧測定、血糖測定、服薬管理、軽度の医療処置などが安全に実施されます。
栄養士による栄養指導も重要なサービスです。糖尿病や腎臓病などの疾患に応じた食事指導や、嚥下機能に配慮した食事形態の提案などが行われます。
デイケアのメリットと専門性

デイケアには、医療・リハビリの専門性を活かした多くのメリットがあります。
身体機能の改善効果が最大のメリットです。専門的なリハビリテーションにより、歩行能力の向上、筋力増強、関節可動域の改善などが期待できます。脳梗塞後のリハビリや骨折後の機能回復において、高い効果が報告されています。
医学的安全性の確保も重要なメリットです。医師・看護師の常駐により、慢性疾患の管理や急変時の対応が適切に行われます。高血圧、糖尿病、心疾患などの既往がある方も安心して利用できます。
個別性の高いプログラムも特徴です。理学療法士や作業療法士による詳細な評価に基づき、一人ひとりの目標に応じたリハビリプランが作成されます。
退院後の継続支援として、病院からの移行がスムーズに行われることも大きな利点です。入院中のリハビリを継続でき、在宅復帰に向けた段階的な支援が可能です。
デイサービスとデイケアの費用比較と負担軽減制度
デイサービスとデイケアの費用について、具体的な金額と負担軽減制度を詳しく解説します。
デイサービスとデイケアの基本料金比較

デイサービスとデイケアの費用は、どちらも介護保険が適用されますが、料金設定に違いがあります。
デイサービスの基本料金(1割負担の場合)は以下の通りです:
要介護1:1日約655円、要介護2:1日約773円、要介護3:1日約896円、要介護4:1日約1,018円、要介護5:1日約1,142円
デイケアの基本料金(1割負担の場合)は以下の通りです:
要介護1:1日約757円、要介護2:1日約894円、要介護3:1日約1,032円、要介護4:1日約1,199円、要介護5:1日約1,364円
デイケアの方がやや高額な設定となっていますが、これは医師・看護師・リハビリ専門職の配置や、専門的な設備・機器の維持費用が反映されているためです。
実費負担と追加料金の詳細

基本料金に加えて、以下の実費負担が発生します。
食費は1食あたり500円~700円程度が一般的です。栄養士による献立作成や、治療食への対応がある場合は、やや高めの設定となることがあります。
おやつ代は1日100円~200円程度で、手作りおやつや季節の特別メニューが提供される施設もあります。
日用品費として、おむつ代、タオル代、レクリエーション材料費などが別途請求される場合があります。月額2,000円~5,000円程度が目安です。
送迎費は基本料金に含まれることが多いですが、送迎範囲外の場合や特別な対応が必要な場合は、別途料金が発生することがあります。
負担軽減制度と利用可能な支援

費用負担を軽減するための制度も充実しています。
高額介護サービス費により、月額の自己負担上限額が設定されています。一般的な所得の世帯では月額44,400円、低所得世帯では24,600円または15,000円が上限となります。
負担限度額認定を受けることで、食費の軽減が可能です。住民税非課税世帯の場合、食費が1食390円まで軽減されます。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度では、低所得の方の利用料が最大25%軽減される場合があります。
デイサービスとデイケアの選び方―状況別判断基準
デイサービスとデイケアのどちらを選ぶべきか、具体的な判断基準と実際のケースを通じて解説します。
身体状況による選択基準

利用者の身体状況に応じた選択基準をご説明します。
デイケアを選ぶべき場合
– 脳梗塞、脳出血などの脳血管障害の既往がある方
– 骨折後のリハビリが必要な方
– パーキンソン病などの神経疾患がある方
– 退院後の継続的なリハビリが必要な方
– 歩行能力や日常生活動作の改善を目指したい方
– 医学的管理が必要な慢性疾患がある方
デイサービスを選ぶべき場合
– 身体機能が比較的安定している方
– 社会交流や外出機会を重視したい方
– 家族の介護負担軽減が主目的の方
– 入浴サービスを必要とする方
– 認知症で環境変化に敏感な方
– レクリエーション活動に興味がある方
利用目的による選択のポイント

利用する目的によっても選択基準が変わります。
機能回復・向上を重視する場合は、デイケアが適しています。専門的なリハビリテーションにより、歩行能力の改善、筋力増強、日常生活動作の向上が期待できます。退院後間もない時期や、身体機能の低下が気になる段階では、デイケアの専門性が効果的です。
生活の質向上・社会参加を重視する場合は、デイサービスが適しています。レクリエーション活動や他の利用者との交流により、生活の楽しみや社会的なつながりを得ることができます。
家族の負担軽減を主目的とする場合は、利用者の身体状況に応じてどちらでも効果的ですが、入浴サービスの充実度や利用時間の長さを考慮して選択します。
段階的な利用も有効な選択肢です。退院直後はデイケアで集中的にリハビリを行い、身体機能が安定した後にデイサービスに移行するパターンも多く見られます。
実際の選択事例とケーススタディ

実際の選択事例をご紹介します。
事例1:脳梗塞後のAさん(78歳男性)
脳梗塞により左半身に軽度の麻痺が残ったAさんは、退院後にデイケアを選択しました。理学療法士による歩行訓練と作業療法士による日常生活動作訓練により、6ヶ月後には杖歩行が可能となり、家事動作も改善しました。
事例2:認知症のBさん(82歳女性)
軽度認知症のBさんは、医療的なケアよりも社会交流を重視してデイサービスを選択しました。馴染みやすい環境で他の利用者と交流し、手工芸などの活動を楽しんでいます。家族の介護負担も軽減され、良好な関係を維持しています。
事例3:段階的利用のCさん(75歳男性)
大腿骨骨折で手術を受けたCさんは、退院後3ヶ月間デイケアで集中的なリハビリを実施。歩行能力が改善した後、社会交流を重視してデイサービスに移行し、現在も週3回利用しています。
利用開始の流れと注意すべきポイント
デイサービスとデイケアを実際に利用する際の手続きや注意点について、詳しく解説します。
デイサービス利用開始の流れ

デイサービスの利用開始は、比較的簡単な手続きで進められます。
ケアマネジャーへの相談から始まります。利用希望時期、頻度、重視したいサービス内容について相談し、適切な施設を提案してもらいます。複数の施設を比較検討することをおすすめします。
施設見学と体験利用を実施します。施設の雰囲気、スタッフの対応、他の利用者の様子、提供されるサービス内容を実際に確認します。本人と一緒に見学することで、環境への適応可能性を判断できます。
利用契約の締結では、サービス内容、利用日時、料金、注意事項などを詳しく確認します。重要事項説明書の内容をしっかりと理解し、不明な点は遠慮なく質問します。
初回利用準備として、持参物の確認、健康状態や注意事項の共有、緊急連絡先の登録などを行います。
デイケア利用開始の流れと特別な手続き

デイケアの利用開始には、医療的な手続きが必要です。
主治医への相談と診療情報提供書の作成が必要です。現在の身体状況、必要なリハビリ内容、医学的注意事項などが記載された書類を準備してもらいます。
デイケア施設での医師面談を受けます。提供される診療情報をもとに、デイケア医師が利用者の状態を評価し、リハビリテーション計画を作成します。
リハビリ専門職による評価も実施されます。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、身体機能や認知機能の詳細な評価を行い、個別のリハビリプログラムを策定します。
利用開始までは、医師面談から1~2週間程度要することが一般的です。デイサービスよりも手続きに時間がかかることを考慮して、早めの相談をおすすめします。
利用時の重要な注意点とトラブル予防

利用時に注意すべき重要なポイントをお伝えします。
持参物の管理も重要です。貴重品は基本的に持参せず、必要最小限の現金のみにします。衣類や日用品には名前を記入し、紛失や取り違いを防ぎます。
体調不良時の対応について事前に確認します。発熱や体調不良の基準、キャンセル連絡の方法、振替利用の可否などを把握しておきます。
送迎時の注意事項として、乗降場所の安全確保、送迎時間の調整、遅刻や早退の連絡方法なども確認が必要です。
他の利用者との関係で問題が生じた場合は、速やかにスタッフに相談します。無理に我慢せず、適切な環境調整を依頼することが大切です。

デイサービスとデイケアの違いで迷ったら、体験利用を上手に活用してくださいね。実際に利用してみると、本人の反応や施設の雰囲気がよくわかりますよ。
専門家に相談することの重要性
デイサービスとデイケアの選択において、専門家のアドバイスを受けることは非常に重要です。適切なサービス選択により、利用者の生活の質向上と家族の負担軽減を効果的に実現できます。
医療・介護の専門家への相談

まず相談すべきは、現在関わっている医療・介護の専門家です。
主治医は、利用者の病状や身体機能を最もよく理解しているため、リハビリの必要性や医学的配慮事項について的確なアドバイスを提供できます。デイケアの利用に必要な診療情報提供書の作成も依頼できます。
ケアマネジャーは、介護保険制度に精通しており、地域のサービス事業所の詳細な情報を持っています。利用者の状況に応じた最適な施設選択や、他のサービスとの組み合わせについても相談できます。
理学療法士や作業療法士からは、身体機能や日常生活動作の観点から、どちらのサービスがより効果的かについて専門的なアドバイスを受けることができます。
地域の相談窓口の活用

地域の相談窓口も重要な情報源です。
地域包括支援センターでは、高齢者とその家族に対する総合的な相談支援を行っています。デイサービスとデイケアの基本的な違いから、地域の事業所情報、利用の流れまで詳しく説明してもらえます。
市区町村の介護保険担当窓口では、制度の詳細や費用負担軽減制度について相談できます。また、地域密着型サービスの情報も提供されます。
社会福祉協議会では、介護者支援に関する相談や情報提供を行っています。同じような経験を持つ家族との交流機会なども紹介してくれます。
専門相談サービスでの個別相談

複雑な状況や個別性の高いケースでは、専門的な相談サービスを利用することも有効です。
特に、「デイサービスとデイケアのどちらが良いか判断がつかない」「本人が利用を嫌がっているが説得方法がわからない」「費用負担が心配」といった悩みは、専門的な知識と経験を持つ相談員からのアドバイスが非常に有効です。
まとめ。あなたに最適なサービス選択のために
デイサービスとデイケアは、どちらも在宅生活を支える重要なサービスですが、目的やサービス内容、医療体制などに明確な違いがあります。
最も重要な判断基準は利用目的です。身体機能の回復・向上を目指したい場合はデイケア、生活支援や社会交流を重視したい場合はデイサービスが適しています。また、医学的管理が必要な方や退院後のリハビリが必要な方は、デイケアの専門性が効果的です。
費用面では、デイケアの方がやや高額ですが、専門的なリハビリテーションや医療的ケアの内容を考慮すると妥当な水準です。負担軽減制度も充実しているため、経済的な心配がある場合は事前に確認しましょう。
利用開始の手続きでは、デイケアの方が医師の診断書などが必要で時間がかかりますが、デイサービスは比較的スムーズに利用開始できます。
在宅介護は長期間にわたる取り組みです。デイサービスとデイケアの違いを正しく理解し、利用者の状態変化に応じて柔軟にサービスを選択することで、持続可能で質の高い在宅生活を実現していきましょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。