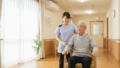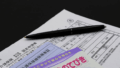「65歳になったら介護保険料はいくら払うの?」「住んでいる地域によって金額が違うって本当?」「収入が少なくても保険料は安くならないの?」
65歳を迎えると、それまで給与天引きされていた介護保険料の徴収方法が変わり、金額も大きく変動する可能性があります。多くの方が驚かれるのは、住んでいる市町村や所得によって保険料に大きな差があることです。同じ県内でも2倍以上の差があることも珍しくありません。
また、65歳以上の介護保険料には、低所得者向けの軽減制度や減免制度があることを知らない方も多く、本来受けられる負担軽減を逃している場合があります。制度を正しく理解し、適切に活用することで、家計の負担を大幅に軽減することも可能です。
この記事では、65歳以上の介護保険料の基本的な仕組みから、地域差や所得段階による違い、利用できる軽減制度まで、わかりやすく詳しく解説します。あなたの保険料がいくらになるのか、負担を軽減する方法はないのかを確認するための完全ガイドです。
65歳以上の介護保険料の基本的な仕組みと全国平均額
65歳以上になると、介護保険制度における位置づけが「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変わり、保険料の算定方法や徴収方法が大きく変わります。まず、この基本的な仕組みを理解することが重要です。
第1号被保険者の介護保険料算定の仕組み

65歳以上の介護保険料は、住んでいる市町村(保険者)ごとに決定されます。各市町村が3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて、今後3年間に必要な介護サービス費用を見積もり、そこから保険料基準額が算定されます。
保険料の算定は、介護給付費の23%を65歳以上の第1号被保険者が負担するという原則に基づいています。残りは40~64歳の第2号被保険者が27%、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担する仕組みになっています。
個人の保険料は、市町村の基準額に所得段階に応じた乗率を掛けて決定されます。所得段階は市町村によって異なりますが、一般的に9段階から13段階程度に分かれており、所得が低いほど保険料が安くなる仕組みです。
介護保険料の負担割合
【第1号被保険者(65歳以上)】23%
【第2号被保険者(40~64歳)】27%
【国】25%
【都道府県】12.5%
【市町村】12.5%
※調整交付金により国の負担割合は変動
また、介護保険料は3年を1期とする「事業計画期間」ごとに見直されます。現在は第9期(2024年度〜2026年度)となっており、高齢化の進行や介護サービスの利用増加により、多くの自治体で保険料が上昇傾向にあります。
全国平均額と近年の推移

厚生労働省の最新データによると、第9期(2024年度〜2026年度)における65歳以上の介護保険料の全国平均は、月額6,225円となっています。これは第8期(2021年度〜2023年度)の月額6,014円から約211円(3.5%)の増加となっています。
介護保険制度が始まった第1期(2000年度〜2002年度)の全国平均は月額2,911円でしたので、約20年間で2倍以上に増加していることがわかります。この増加の主な要因は、高齢化の進行による要介護認定者数の増加と、介護サービスの充実によるものです。
ただし、この平均額はあくまでも基準額(所得段階の中間層)の金額であり、実際の個人負担額は所得に応じて0.3倍から3.0倍程度の幅があります。最も所得が低い段階では月額約1,900円程度、最も高い段階では月額約18,700円程度となることもあります。
保険料の徴収方法―特別徴収と普通徴収

65歳以上の介護保険料の徴収方法は、年金受給額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2つに分かれます。これは40~64歳の時のように給与から天引きされる方法とは異なります。
特別徴収は、年額18万円以上の年金を受給している方が対象で、年金から直接保険料が天引きされます。対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などです。年6回の年金支給時に、2か月分ずつ天引きされます。
普通徴収は、年金額が年額18万円未満の方や、年度途中で65歳になった方などが対象で、納付書や口座振替によって保険料を納付します。通常は年8回(7月〜翌年2月)に分けて納付します。
特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年度の保険料額の1/6ずつを仮徴収し、10月・12月・翌年2月に当年度の確定保険料額との差額を調整して本徴収する仕組みになっています。このため、年度前半と後半で徴収額が変わることがあります。
【介護保険料、思ったより高くて驚いていませんか?】
65歳以上の介護保険料。地域別・所得段階別の保険料の違いと具体的な金額
65歳以上の介護保険料は、住んでいる市町村と個人の所得によって大きく異なります。全国で最も高い自治体と低い自治体では3倍近い差があり、同じ自治体内でも所得段階により大きな開きがあります。
都道府県別・市町村別の保険料格差

第9期における介護保険料の地域格差は非常に大きく、最も高い自治体では月額約8,000円を超える一方、最も低い自治体では月額約3,000円台となっています。この差は約2.7倍に達しており、住む場所によって年間で5万円以上の差が生じることもあります。
保険料が高い地域の特徴として、高齢化率が高い、要介護認定率が高い、介護サービス事業所が充実している(その分費用がかかる)、人口密度が低い(効率的なサービス提供が困難)などが挙げられます。
逆に保険料が低い地域は、比較的高齢化率が低い、要介護認定率が低い、介護予防に力を入れている、効率的なサービス提供体制が整っているなどの特徴があります。
保険料が高い地域の例(基準額・月額)
・大阪府守口市:8,037円
・大阪府門真市:7,980円
・奈良県天理市:7,700円
・大阪府大阪市:7,654円
・和歌山県有田市:7,550円
保険料が低い地域の例(基準額・月額)
・埼玉県戸田市:3,500円
・千葉県浦安市:3,600円
・東京都小金井市:3,800円
・神奈川県寒川町:4,000円
・愛知県幸田町:4,100円
都道府県別でみると、大阪府、奈良県、和歌山県、福岡県、沖縄県などで保険料が高い傾向にあり、一方で埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、長野県などで比較的低い傾向があります。ただし、同じ都道府県内でも市町村によって大きな差があることに注意が必要です。
所得段階による保険料の違い

65歳以上の介護保険料は、本人や世帯の所得に応じて段階的に設定されています。多くの市町村では9段階から13段階程度に分かれており、所得が低いほど保険料が安くなる応能負担の仕組みが採用されています。
所得段階の判定は、前年の所得をもとに行われます。住民税の課税状況、合計所得金額、年金収入額などを総合的に判断して決定されます。世帯全体が住民税非課税の場合は低い段階となり、本人の所得が高いほど高い段階となります。
具体例として、基準額が月額6,000円の市町村の場合を見てみましょう。第1段階の方は月額1,800円(年額21,600円)となる一方、第9段階の方は月額10,200円(年額122,400円)となり、約5.7倍の差が生じます。
所得段階の判定で注意すべき点は、遺族年金や障害年金は非課税所得のため所得に含まれないこと、同居家族の所得も判定に影響すること、前年の所得で判定されるため退職直後は高い段階になる可能性があることなどです。
保険料が高くなる要因と地域特性

介護保険料が高くなる要因は複数ありますが、最も大きな要因は高齢化率の高さです。65歳以上人口の割合が高い地域では、介護サービスの需要が多く、必然的に保険料も高くなります。
要介護認定率も重要な要因です。同じ高齢化率でも、要介護認定を受ける方の割合が高い地域では、介護給付費が多くなり保険料が上昇します。認定率が高い背景には、地域の健康状態、認定基準の違い、介護予防の取り組み状況などがあります。
また、介護サービス事業所の整備状況も保険料に影響します。サービス事業所が充実している地域では利用しやすい反面、給付費が増加し保険料上昇につながります。逆に、サービス事業所が不足している地域では、必要なサービスを受けられない問題がある一方で保険料は比較的低く抑えられる傾向があります。

地域による保険料の差は、単純に高い・安いだけでは判断できません。保険料が高い地域は介護サービスが充実している場合が多く、将来介護が必要になった時により良いサービスを受けられる可能性があります。逆に保険料が安い地域はサービスが限定的な場合もあるんですね。
人口密度も重要な要因の一つです。人口が少ない過疎地域では、介護サービスを効率的に提供することが困難で、1人当たりのサービス提供コストが高くなりがちです。これが保険料の上昇につながる場合があります。
65歳以上の介護保険料の軽減・減免制度と負担軽減の方法
65歳以上の介護保険料には、低所得者の負担を軽減するためのさまざまな制度があります。これらの制度を適切に活用することで、保険料を大幅に軽減することが可能です。しかし、制度の存在を知らなかったり、申請方法がわからなかったりして、恩恵を受けられていない方も多くいらっしゃいます。
公費による保険料軽減制度

2019年10月から開始された「介護保険料の軽減強化」は、消費税率引き上げに伴う社会保障充実策の一環として実施されている制度です。住民税非課税世帯の方を対象に、国と自治体が公費を投入して保険料を軽減しています。
この制度により、所得段階第1段階から第3段階の方の保険料負担が軽減されています。軽減は自動的に適用されるため、対象者が特別な申請を行う必要はありません。住民税の課税状況と所得金額により、市町村が自動的に判定し、軽減後の保険料が通知されます。
公費による軽減内容
【第1段階】0.50倍→0.30倍(軽減率40%)
・老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
・世帯全員住民税非課税で本人年金収入80万円以下
【第2段階】0.75倍→0.50倍(軽減率33%)
・世帯全員住民税非課税で本人年金収入80万円超120万円以下
【第3段階】0.75倍→0.70倍(軽減率7%)
・世帯全員住民税非課税で本人年金収入120万円超
例えば、基準額が月額6,000円の自治体の場合、第1段階の方は軽減前の月額3,000円(0.50倍)から月額1,800円(0.30倍)となり、年間で14,400円の軽減効果があります。
市町村独自の減免制度

公費による軽減制度とは別に、多くの市町村が独自の減免制度を設けています。この制度は、災害や失業、事業の廃止など特別な事情により、保険料の納付が困難になった方を対象としています。
市町村独自の減免制度は、申請が必要で、審査により適用可否が決定されます。減免の内容は自治体によって異なりますが、保険料の全額免除から一部減額まで幅広い支援が用意されています。
減免を申請する場合は、住んでいる市町村の介護保険担当課に相談することから始めます。必要書類は自治体によって異なりますが、一般的には収入証明書、預貯金通帳のコピー、医療費の領収書、災害証明書などが必要となります。
申請期限も自治体によって異なるため、早めに相談することが重要です。多くの自治体では、保険料の納期限前までに申請することを条件としています。
負担軽減を受けるための手続きと注意点

介護保険料の軽減制度を適切に活用するためには、制度の内容を理解し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。公費による軽減は自動適用ですが、市町村独自の減免制度は申請が必要です。
まず、自分がどの所得段階に該当するかを確認することから始めましょう。毎年送付される介護保険料決定通知書に所得段階が記載されています。所得段階が間違っている場合や、収入状況に変化があった場合は、市町村に相談することが大切です。
減免制度の申請をする場合は、以下の点に注意が必要です:
また、介護保険料を滞納している場合は、給付制限のペナルティが課される可能性があります。保険料の納付が困難な場合は、滞納する前に市町村に相談し、分割納付や減免制度の活用を検討することが重要です。
専門相談では、介護保険料の軽減制度だけでなく、その他の生活支援制度、介護サービスの利用方法、家族の負担軽減方法など、包括的なサポートを受けることができます。また、複雑な手続きについても、具体的な方法や必要書類について詳しい指導を提供しています。
初回20分の無料相談では、現在の状況を整理し、利用できる制度や軽減方法について具体的なアドバイスを受けることができます。夜間にも対応しているため、日中は仕事や介護で忙しい方でも利用しやすくなっています。
「家計の負担を少しでも軽減したい」「利用できる制度を知りたい」「手続きの方法がわからない」といった場合は、専門家のサポートを活用することで、適切な制度利用により経済的負担を軽減することができるでしょう。
まとめ。65歳以上の介護保険料を正しく理解し、負担軽減策を活用しよう
65歳以上の介護保険料は、全国平均で月額6,225円となっていますが、住んでいる市町村と個人の所得によって大きく異なります。最も高い自治体と低い自治体では3倍近い差があり、同じ自治体内でも所得段階により最大で5倍以上の差が生じます。
保険料の算定は3年ごとに見直され、高齢化の進行とともに上昇傾向が続いています。しかし、低所得者に対する軽減制度や市町村独自の減免制度を適切に活用することで、負担を大幅に軽減することが可能です。
徴収方法は年金受給額により特別徴収と普通徴収に分かれ、65歳になったばかりの方は徴収方法が切り替わるまで時間がかかる場合があります。保険料の通知書は大切に保管し、所得段階や徴収方法に疑問がある場合は早めに市町村に確認することが大切です。
公費による軽減制度は住民税非課税世帯を対象に自動適用されますが、市町村独自の減免制度は申請が必要です。災害や失業、収入減少などの特別な事情がある場合は、制度の活用を検討しましょう。
保険料を滞納すると将来介護サービスを利用する際に給付制限を受ける可能性があるため、納付が困難な場合は早めに相談することが重要です。分割納付の相談も可能です。
介護保険料の制度は複雑で、自治体ごとに異なる部分も多いため、一人で判断せず専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。適切な制度活用により、家計の負担を軽減しながら、将来の介護に備えることができるでしょう。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。