「デイサービスを利用し始めてから、母の認知症が急に悪化したような気がする」「施設で過ごした後、帰宅してから興奮状態が続いて困っている」「デイサービスが逆効果になっているのではないか心配」
このような悩みを抱える家族は少なくありません。認知症の方がデイサービスを利用した際に症状が悪化したように見える現象は、決して珍しいことではなく、適切な理解と対応により改善可能な問題です。
認知症の症状悪化には、環境の変化、不適切なケア、家族や施設の理解不足など、様々な要因が複雑に絡み合っています。しかし、これらの原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、デイサービスを認知症の方にとって有益なサービスとして活用することができます。この記事では、認知症がデイサービスで悪化する具体的な原因を分析し、症状改善につながる実践的な対策をお伝えします。
認知症の症状がデイサービスで悪化する原因と背景
環境変化によるせん妄とBPSD(行動・心理症状)の増悪

認知症の方がデイサービス利用開始後に症状が悪化する最も多い原因は、環境変化によるせん妄とBPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)の増悪です。
せん妄は、急激な意識レベルの変動、注意力の低下、思考の混乱、現実感の喪失などを特徴とする急性の意識障害です。認知症の方は、健常者と比べてせん妄を起こしやすく、新しい環境に置かれることで発症リスクが高まります。
デイサービス利用開始時によく見られるせん妄症状
【意識・睡眠の変化】
・夜間の不眠や昼夜逆転
・日中の過度な眠気
・意識レベルの変動
【精神症状】
・幻覚や妄想の出現・増強
・興奮状態や暴言・暴力の増加
・極度の不安や恐怖感
【認知機能】
・記憶の混乱
・見当識障害の悪化
・注意力の著しい低下
認知症の方にとって、慣れ親しんだ自宅以外の場所で過ごすことは大きなストレスとなります。新しい場所、知らない人々、異なる日課やルール。これらすべてが認知機能に負荷をかけ、既存の症状を悪化させる可能性があります。
特に軽度から中等度の認知症の方では、「いつもと違う」という違和感を強く感じながらも、その状況を理解し適応することが困難なため、強い不安と混乱を経験します。
不適切なケアや刺激による認知機能の混乱
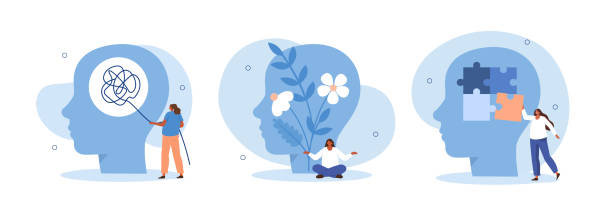
デイサービスでの不適切なケアや過度な刺激も、認知症症状の悪化要因となります。認知症の方は情報処理能力が低下しているため、健常者にとって適切な刺激でも、認知症の方には過度な負荷となることがあります。
大音量の音楽や騒がしい環境、複数の活動が同時進行する混雑した空間、明るすぎる照明や点滅する光、強い匂いや不快な臭い、多人数での同時活動やレクリエーションなどが挙げられます。これらの刺激により、認知症の方は情報処理が追い付かず、混乱状態に陥ることがあります。
また、すべての利用者に同じプログラムを提供する画一的なアプローチも問題となります。認知症の方一人ひとりは、認知機能レベル、興味関心、身体機能、性格などが大きく異なります。本人の能力を超えた難しい活動を強要したり、興味のない活動への無理な参加を求めたり、体力や集中力を超えた長時間の活動を実施したりすることで、本人にとって大きなストレスとなってしまいます。
デイサービスでの服薬管理の問題も症状悪化につながることがあります。服薬時間のずれによる薬効の変化、薬の飲み忘れや重複投与、他の利用者の薬との取り違え、薬の副作用に対する観察不足などは、認知症の症状を不安定にする要因となります。
家族の誤解と施設の専門性不足が引き起こす悪循環
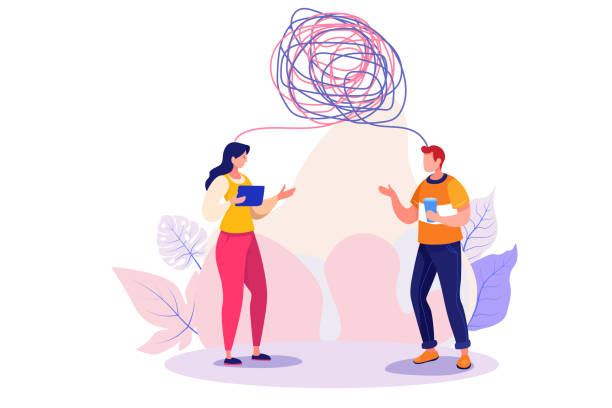
認知症症状の悪化には、家族の誤解と施設の専門性不足による悪循環も大きく影響します。
多くの家族は、認知症の進行とデイサービス利用開始のタイミングが重なることで、「デイサービスが原因で悪化した」と誤解してしまいます。「施設で何か嫌なことをされているに違いない」「無理やり活動させられて疲れているのではないか」「他の利用者とトラブルがあったのかもしれない」「スタッフの対応が悪いせいで症状が悪化した」といった思い込みを持ちやすくなります。
残念ながら、すべてのデイサービスが認知症ケアの十分な専門性を持っているわけではありません。認知症の症状や対応方法に関する知識不足、BPSD(行動・心理症状)への不適切な対応、個別ケアプランの作成・実施能力の不足、医療機関や家族との連携不足、症状変化に対する観察・記録能力の不足などが問題となることがあります。
施設の専門性不足による問題点
【知識・技術面】
・認知症の症状や対応方法の理解不足
・BPSD対応の技術不足
・個別ケアプラン作成能力の不足
【体制面】
・人手不足による質の低下
・研修不足のスタッフによるケア
・利用者一人ひとりに向き合う時間不足
【連携面】
・家族、医療機関との情報共有不足
・症状変化の記録・報告体制の不備
・ケアプラン見直しの遅れ
認知症の悪化を防ぐデイサービス選びと利用方法
認知症専門デイサービスの見極めポイント

認知症症状の悪化を防ぐためには、認知症ケアに特化した専門性の高いデイサービスを選ぶことが重要です。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)は、認知症の方を専門的にケアする小規模なデイサービスです。一般的なデイサービスとは異なり、利用定員が12人以下の小規模運営で、認知症ケア専門の研修を受けたスタッフが配置されています。個別ケアを重視したプログラム設計、家庭的で落ち着いた環境設定、地域密着型サービスとしての位置づけなどが特徴です。
実際に施設を見学する際は、利用者の表情が穏やかで安心している様子か、スタッフが利用者一人ひとりに丁寧に関わっているか、活動への参加が強制的ではなく自然な流れで行われているか、利用者同士の関係が良好でトラブルが起きていないかなどを注意深く観察しましょう。
段階的利用と個別ケアプランの重要性

認知症症状の悪化を防ぐためには、段階的な利用開始と個別ケアプランの作成が不可欠です。
段階的利用は、急激な環境変化によるストレスを最小限に抑える効果的な方法です。まず事前面談と環境への慣れの段階では、家族同伴での施設見学、スタッフとの顔合わせと関係構築、短時間(1~2時間)の体験利用、本人の反応と適応状況の評価を1~2週間かけて行います。
段階的利用の3つのステップ
【第1段階:事前面談・環境慣れ(1~2週間)】
・家族同伴での施設見学
・スタッフとの顔合わせ
・短時間(1~2時間)の体験利用
・本人の反応と適応状況の評価
【第2段階:短時間利用開始(2~4週間)】
・3~4時間程度の利用開始
・送迎時と施設での様子観察
・帰宅後の状態変化モニタリング
・利用時間・内容の調整
【第3段階:標準利用への移行(4~8週間)】
・徐々に利用時間延長
・様々なプログラムへの参加
・他利用者との交流促進
・安定した利用パターン確立
個別ケアプランの作成では、まず認知機能アセスメントを行います。認知症の種類と重症度の評価、残存機能と低下している機能の把握、BPSD(行動・心理症状)の有無と特徴、日常生活動作(ADL)の自立度評価などを詳細に行います。
BPSD対応に優れた施設の特徴と選び方

BPSD(行動・心理症状)への適切な対応ができる施設を選ぶことは、症状悪化の防止に極めて重要です。
不安・抑うつへの対応では、本人の気持ちに共感し安心できる言葉かけができること、一対一での対話時間を確保していること、好きな音楽や馴染みのある環境を提供していること、無理に元気づけず本人のペースを尊重していることなどが重要です。
興奮・易怒性への対応では、興奮の前兆を見逃さず早期に対応できること、刺激的な環境や言動を避けるノウハウがあること、興奮時には安全を確保しつつ冷静に対応できること、興奮の原因を分析し予防策を講じていることなどが求められます。
見学時には、BPSD症状を持つ利用者への実際の対応を観察させてもらいましょう。スタッフが利用者の感情に寄り添った対応をしているか、強制的や威圧的な態度を取っていないか、個々の症状に応じた適切な対応ができているか、チームワークを取って一貫した対応をしているかなどをチェックします。
症状悪化時の対応と家族・施設・医療の連携体制
急激な症状悪化への緊急対応と医療機関との連携

認知症の症状が急激に悪化した場合、迅速で適切な対応が必要です。特にBPSD(行動・心理症状)の急激な悪化は、本人の安全や周囲への影響を考慮して、緊急性の高い対応が求められます。
急激な症状悪化のサインとしては、身体的症状では発熱や血圧の急激な変化、意識レベルの低下や朦朧状態、歩行困難や転倒リスクの増大、食事摂取量の急激な減少、脱水症状や栄養状態の悪化などがあります。
デイサービスでの緊急時には、まず本人と周囲の利用者の安全を最優先に確保し、症状の詳細な観察と記録を行います。看護師による医学的判断でバイタルサインの測定と医学的評価を実施し、家族への連絡で状況の説明と今後の対応についての相談を行います。必要に応じて主治医や救急医療機関への連絡も行います。
医療機関との連携体制
【主治医との日常連携】
・定期的な情報共有と相談体制
・緊急時連絡方法の事前確認
・薬物調整時の情報共有
・観察記録の医師への提供
【専門医療機関との連携】
・認知症疾患医療センター
・精神科医によるBPSD専門治療
・入院調整と情報提供
・退院時の連携継続
【救急医療機関との連携】
・緊急搬送時の情報提供
・基本情報の整理保管
・服薬情報や既往歴の把握
・家族連絡先の明確化
家族の理解促進と介護技術向上のサポート

症状悪化の予防と改善には、家族の理解促進と介護技術の向上が不可欠です。
家族教育では、認知症の基礎知識として、認知症の種類と症状の理解、病気の進行過程と予後の説明、BPSD(行動・心理症状)の理解と対応方法、薬物療法と非薬物療法の基本知識などを学ぶことが大切です。
コミュニケーション技術では、認知症の方との効果的な会話方法、否定や訂正を避ける接し方、本人の感情に寄り添う共感技術、非言語コミュニケーションの活用などを身につけることが重要です。
家族の心理的サポートも重要な要素です。介護ストレスは症状悪化の大きな要因となるため、家族自身のストレス管理が重要です。定期的な休息(レスパイトケア)の確保、家族会や支援グループへの参加、カウンセリングや心理的サポートの利用、健康管理と趣味・社会活動の継続などを心がけましょう。
多職種チームによる継続的モニタリング体制

症状悪化の予防と早期発見には、多職種チームによる継続的なモニタリング体制が重要です。
モニタリングチームには、医療職として主治医(全体的な医学的管理と治療方針の決定)、精神科医・認知症専門医(BPSD症状の専門的評価と治療)、看護師(日常的な健康状態の観察と医療的ケア)、薬剤師(服薬管理と薬物相互作用のチェック)が参加します。
多職種チーム構成と役割
【医療職】
・主治医:全体的な医学管理と治療方針決定
・精神科医:BPSD症状の専門評価と治療
・看護師:日常健康観察と医療ケア
・薬剤師:服薬管理と薬物相互作用チェック
【介護職】
・ケアマネジャー:ケアプラン調整と見直し
・デイサービススタッフ:日常観察と記録
・訪問介護ヘルパー:自宅生活状況把握
【その他専門職】
・臨床心理士:心理評価とカウンセリング
・作業療法士:ADL評価と訓練
・ソーシャルワーカー:社会資源調整
継続的モニタリングでは、月1回の多職種カンファレンス、3ヶ月ごとの包括的評価、6ヶ月ごとのケアプラン見直し、年1回の総合的な医学的評価などを定期的に実施します。
症状悪化の早期発見には、日常生活の変化、コミュニケーションの変化、行動・感情の変化などに注目することが重要です。いつもできていたことができなくなった、好きだった活動に興味を示さなくなった、食事や睡眠のパターンが大きく変わった、身だしなみへの関心がなくなったなどの日常生活の変化を見逃さないようにしましょう。
まとめ。適切な理解と対応で症状改善を目指す
認知症がデイサービスで悪化するという現象は、環境変化によるせん妄、不適切なケア、家族や施設の理解不足など、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。しかし、これらの原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、デイサービスを認知症の方にとって有益なサービスとして活用することができます。
重要なのは、認知症専門の知識と技術を持つデイサービスを選び、段階的な利用開始と個別ケアプランの作成を行うことです。また、BPSD(行動・心理症状)への適切な対応ができる施設を選択し、症状悪化時には迅速で適切な対応が取れる体制を整えることが不可欠です。
家族、施設、医療機関が連携し、多職種チームによる継続的なモニタリング体制を構築することで、症状の早期発見と適切な対応が可能になります。特に、家族の理解促進と介護技術の向上、そして適切な相談・支援体制の活用が重要です。

認知症介護では一人で悩まず、専門家の力を借りることが大切です。夜中の不安や、誰にも相談できない深刻な悩みを抱えた時は、「ココマモ」のようなオンライン相談サービスなどを活用して、専門的なサポートを受けることができます。認知症の症状悪化への不安、デイサービス選びの悩み、介護疲れなど、あらゆる相談に専門的に対応していますよ。
さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。






