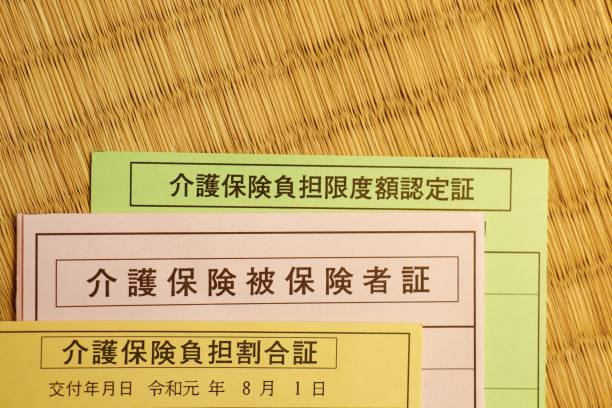「介護保険料っていつから支払うの?」「40歳になったら自動的に始まるの?」「65歳になったら何か変わるの?」
介護保険制度について、保険料の支払い開始時期や納付方法について疑問を持っている方は多いでしょう。介護保険料は40歳から支払い義務が発生しますが、具体的にいつから始まるのか、どのような方法で納付するのかは、年齢や就労状況によって異なります。
この記事では、介護保険料がいつから支払い義務が発生するのか、年齢別の納付方法の違い、最新の制度改正情報まで、わかりやすく詳しく解説します。適切な納付を行い、将来の介護サービス利用に備えるための知識を身につけましょう。
介護保険料はいつから支払い義務が発生するのか
介護保険料の支払いは、40歳の誕生日の前日が属する月から始まります。つまり、誕生日によって支払い開始月が変わる場合があり、特に1日生まれの方は注意が必要です。また、65歳になると第1号被保険者となり、支払い方法も変わります。
40歳から始まる第2号被保険者の介護保険料

介護保険料はいつから支払い義務が発生するかというと、基本的には満40歳に達した時から始まります。この「満40歳に達した時」というのは、40歳の誕生日の前日のことを指し、その日が属する月から介護保険料の支払いが開始されます。
支払い開始時期の具体例
✅ 5月15日生まれの場合
5月14日が「満40歳に達した日」→ 5月分から保険料開始
✅ 6月1日生まれの場合
5月31日が該当日 → 5月分から保険料開始
✅ 1日生まれの特例
前月末に満年齢達成とみなされ、前月分から開始
40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」と呼ばれ、医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入していることが介護保険加入の条件となります。つまり、医療保険に加入していない方は介護保険料を支払う必要がありません。
第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と一体となって徴収されます。給与所得者の場合は健康保険料と合わせて給与から天引きされ、自営業者の場合は国民健康保険料と一緒に納付書で支払うことになります。
65歳から変わる第1号被保険者の介護保険料

65歳になると介護保険制度での位置づけが大きく変わります。65歳の誕生日が属する年度の4月1日から「第1号被保険者」となり、介護保険料の納付方法や保険料額の決定方法も変更されます。
第1号被保険者になると、介護保険料は健康保険料とは別に算定・徴収されるようになります。保険料額は住民税の課税状況や前年の所得に基づいて、お住まいの市区町村が段階別に決定します。
65歳以降の介護保険料がいつから新しい計算方法になるかというと、65歳の誕生日が属する年度の4月分からです。例えば、誕生日が7月15日の方でも、その年の4月分から第1号被保険者としての保険料が適用されます。
誕生日が1日の場合の特別な注意点

介護保険料がいつから発生するかを考える上で、特に注意が必要なのが誕生日が1日の方です。民法の年齢計算に関する法律により、誕生日が1日の場合は前月末に満年齢に達したとみなされるため、保険料の支払い開始時期が他の日生まれの方と異なります。
この特別な取り扱いは、65歳で第1号被保険者になる際にも適用されます。5月1日生まれの方は、4月30日に満65歳に達したとみなされるため、その年度の4月から第1号被保険者としての保険料が適用されます。
1日生まれの方が注意すべき点は、予想より1か月早く保険料の支払いが開始される可能性があることです。特に40歳になる際は、給与明細を確認して介護保険料の天引きが始まっていないか確認することをお勧めします。

この1日生まれの特例は法律で定められているため例外はありません。知らずに未払いになってしまうトラブルを避けるためにも、該当する方は事前に準備をしておくことが大切ですね。
介護保険料の支払い方法と納付スケジュール
介護保険料の支払い方法は、年齢や就労状況によって大きく異なります。それぞれの特徴を理解して、適切な納付を行いましょう。
40歳から64歳までの健康保険料と一体での納付

40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と一体になって徴収されます。介護保険料がいつから天引きされるかは、加入している医療保険の種類によって納付方法とタイミングが異なります。
加入保険別の納付方法
✅ 会社員・公務員(職域保険)
・健康保険料と合わせて毎月の給与から天引き
・給与明細に「介護保険料」として別途記載
・賞与からも同様に天引き
✅ 自営業者・無職(国民健康保険)
・「介護納付金分」として国民健康保険料と一体で請求
・納付書による支払いや口座振替での自動引き落とし
・年間保険料を複数回に分けて納付
会社員や公務員など職域保険に加入している方の場合、介護保険料は健康保険料と合わせて毎月の給与から天引きされます。給与明細には「介護保険料」として別途記載されることが多く、健康保険料と同じタイミングで控除されます。
自営業者や無職の方が加入する国民健康保険では、介護保険料は「介護納付金分」として国民健康保険料と一体で請求されます。納付書による支払いや口座振替での自動引き落としが一般的で、年間保険料を複数回に分けて納付します。
扶養に入っている配偶者の場合は、介護保険料を別途支払う必要はありません。扶養者が支払う保険料でカバーされているため、40歳になっても追加の負担は発生しません。
65歳以上の年金天引きと普通徴収の違い

65歳以上の第1号被保険者になると、介護保険料の納付方法が大きく変わります。介護保険料がいつから新しい方法で徴収されるかは、年金受給状況や所得状況によって「特別徴収(年金天引き)」と「普通徴収(納付書払い)」に分かれます。
特別徴収(年金天引き)
✅ 対象者:年額18万円以上の年金受給者
✅ 徴収時期:偶数月の年金支給時(2,4,6,8,10,12月)
✅ 徴収方法:年間保険料を6等分して毎回天引き
✅ メリット:納付忘れがない、手続き不要
普通徴収(納付書払い)
✅ 対象者:年金18万円未満、年金未受給、65歳なりたて
✅ 納付回数:年8回払い(7月〜翌年2月)
✅ 納付方法:納付書または口座振替
✅ 通知時期:毎年6月に保険料額決定通知書を送付
特別徴収は、年金から直接介護保険料が天引きされる方法です。年額18万円以上の年金を受給している方が対象となり、偶数月の年金支給時に介護保険料が差し引かれます。
一方、普通徴収は納付書や口座振替で支払う方法です。年金額が18万円未満の方、年金を受給していない方、65歳になったばかりで特別徴収の準備が整っていない方などが対象となります。
新たに65歳になった方は、最初の1年程度は普通徴収から始まり、その後特別徴収に切り替わることが一般的です。この切り替えには一定の準備期間が必要なため、年金保険者との調整によって決まります。
2025年度の保険料改定と計算方法の変更点

2025年度から介護保険料の計算方法にいくつかの変更が実施されています。介護保険料がいつから新しい計算方法になるかというと、2025年4月分(令和7年度)から適用されています。
最も重要な変更点は、所得指標の表記が「保険料算定用所得金額」に統一されたことです。これまで使用されていた「合計所得金額」から変更され、給与所得者や年金受給者の所得評価方法が見直されています。
各自治体の保険料設定も2025年度に見直しが行われています。例えば横浜市では、基準額(第5段階)は月額約6,600円程度に設定され、所得に応じて最低約1,800円から最高約20,000円まで幅広く設定されています。
また、低所得者に対する軽減措置も継続されており、住民税非課税世帯などを対象とした保険料軽減が実施されています。この軽減措置は国と自治体が費用を負担する仕組みとなっており、対象者は自動的に軽減された保険料が適用されます。
介護保険料の免除・軽減制度と滞納時のペナルティ
介護保険料の支払いが困難な場合の救済制度と、滞納した場合のペナルティについて詳しく解説します。
保険料軽減の対象者と申請方法

介護保険料には、経済的に困難な方を対象とした軽減制度があります。介護保険料がいつから軽減されるかは、対象者の状況や申請のタイミングによって異なりますが、適切な手続きを行うことで負担を軽減することができます。
最も一般的な軽減制度は、低所得者を対象とした公費による軽減です。住民税非課税世帯で、かつ一定の要件を満たす方が対象となります。世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方などが該当します。
この公費軽減は申請不要で、要件に該当する方は自動的に軽減された保険料が適用されます。軽減割合は所得段階によって異なり、最大で基準額の約3割まで軽減される場合があります。
軽減制度申請の流れ
1. 相談:市区町村の介護保険課へ相談
2. 書類準備:収入証明書、預貯金通帳、住民票など
3. 申請提出:必要書類を窓口で提出
4. 審査:1〜2か月程度の審査期間
5. 適用開始:申請月の翌月分から軽減開始

滞納した場合の延滞金と介護サービス利用への影響

介護保険料を滞納した場合、延滞金の発生と介護サービス利用時のペナルティが課せられます。介護保険料がいつから滞納扱いになるかというと、納期限を過ぎた翌日から滞納が始まり、段階的にペナルティが重くなっていきます。
延滞金は納期限の翌日から発生し、年率は滞納期間によって異なります。納期限から1か月以内は年2.4%程度、1か月を超えると年8.7%程度の延滞金が加算されます(2025年度の利率)。
介護サービス利用への影響は、滞納期間によって段階的に厳しくなります。1年以上滞納すると、介護サービス利用時の支払い方法が「償還払い」に変更されます。通常は利用者負担分(1~3割)のみを事業者に支払えばよいところ、滞納者は一旦全額(10割)を支払い、後で保険給付分の払い戻しを受けることになります。
2年以上滞納すると、最も重いペナルティが課せられます。滞納期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担割合が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費の支給も停止されます。
【介護のお金のこと、正しく理解できていますか?】
支払いが困難な場合の相談窓口

介護保険料の支払いが困難になった場合、一人で抱え込まず適切な相談窓口を利用することが重要です。介護保険料がいつから支払えなくなるかを予想できる場合は、滞納が始まる前に相談することで、より多くの選択肢を検討できます。
相談できる窓口
✅ 市区町村の介護保険課・国民健康保険課
保険料軽減制度、分割納付、納付猶予の相談
✅ 社会福祉協議会
生活福祉資金貸付、就労支援、家計改善支援
✅ 法テラス・弁護士会
法的問題、自己破産・債務整理の相談
✅ 介護家族専門相談サービス「ココマモ」
経済問題と介護の両方に詳しい専門相談員によるサポート
最初に相談すべき窓口は、お住まいの市区町村の介護保険課または国民健康保険課です。ここでは保険料の軽減制度、分割納付、納付猶予などについて相談できます。
経済的困窮の原因が病気や失業などの場合は、社会福祉協議会での相談も有効です。生活福祉資金の貸付、就労支援、家計改善支援などの総合的なサポートを受けることができます。


介護保険料はいつから支払う?まとめ。
介護保険料はいつから支払い義務が発生するかについて、40歳の誕生日の前日が属する月から始まり、65歳で納付方法が変わることを詳しく解説してきました。特に誕生日が1日の方は、前月から支払いが開始される点に注意が必要です。
40歳から64歳までは健康保険料と一体で徴収され、65歳以降は年金天引きまたは納付書での支払いに変わります。2025年度からは所得指標の見直しなど制度改正も実施されており、保険料額に影響する可能性があります。
経済的に困難な場合は軽減制度や相談窓口を活用し、滞納による深刻なペナルティを避けることが重要です。介護保険料は将来の介護サービス利用に直結する重要な制度ですので、適切に理解し、計画的に納付していくことが大切です。
不明な点がある場合は、お住まいの自治体や専門の相談窓口を積極的に活用し、安心して介護保険制度を利用できるよう準備していきましょう。

さいごに。介護の悩みが消えないあなたへ
この記事を読んでも、こんな不安は残っていませんか?
実は、多くの介護家族が同じ悩みを抱えています。
そこに足りないのは「今後どのように行動していくべきか」というあなた自身の判断軸です。
このまま何も変えなければ
介護の判断軸がないままでは、
状況が変わるたびに迷い、
そのたびに自分を責め続けることになります。
「もっと早く考えておけばよかった」
そう思う人を、私たちは何人も見てきました。
毎日3分で「介護の判断軸」を育てる無料メルマガを発信しています。

そこでココマモでは、毎日3分で読める「介護の判断軸」となる知識が学べる無料メールマガジンを発信しています。
具体的には、
さらに、登録した方だけが読める
- メルマガ会員限定記事(介護の決断に特化した深堀りコンテンツ)
にもアクセスできます。
介護の決断を、自分でできるようになるために
介護に「正解」はありません。
だからこそ、最後に自分で納得して選べるかどうかが一番大事です。
そのための小さな一歩として、
まずはメルマガで「判断軸」を一緒に育てていきませんか?
下記フォーム入力後、メールボックスに1通目が届きます。
• メールの最後に必ず解除リンクを記載していますので、いつでもワンクリックで停止できます。
• ご入力いただいた情報は プライバシーポリシーに基づき厳重に管理しています。
• ※Yahoo・iCloudメールは届きにくい場合があります。Gmailまたは携帯メールのご利用を推奨しています。